�T�K�L�^�@�����@�P�P�@�@�@�쑊�n�s������@�|�@�Îl���_��
���쑊�n�s�̌Îl���_��
�@�Q�O�P�O�N�i���Q�Q�j�ɓ���A�V�Ҙ�Õ��y�L�̌Îl���_�Ђ̒T�K��̒T�K�\���̎��O�����E�������n�߂܂����B
�@�T�C�g�w���{�̏�T�K�����������x�ŋM�z���_�ЁE�Îl���Ђ̋L�ڂ������܂����B
�@�쑊�n�s�����摺�㎚�ىz�̖����̂܂ܔp��ɂȂ��������̖{�ېՂɋM�z���_�ЁE�Îl���Ђ��J���Ă���Ƃ����Q�O�O�X�N�P�P���U���̃u���O�L���ł��B
�@����W�̃T�C�g�ɓ�����Ɓw����̌�����O�l�X�����䂭�I�x�ɂ����l�̋L�ڂ�����܂����B
�@����ŏꏊ�͖��m�ɂȂ�܂����B
�@����W�̕����T�C�g�œ쑊�n�s�E���n�s�̑��n�˂̏�ɂ��Ă��낢�닳���Ă��������܂����B
�@�����������E������i�߂Ă����Ƃ���A�����{��k�Ђ��N����Ôg�����P���傫�Ȕ�Q���o�āA������P���q�͔��d���̌��q�F�����g�_�E���ɂ�薢�\�L�̊�@���P��������܂����B
�@�쑊�n�s�̏�����͔��a�Q�O�q�����ɂ���x�����ŗ�������ł��Ȃ��ɂȂ�܂����B
�@�쑊�n�s�̂Q�O�P�P�N�S���U�����݂́w���a�Q�O�q�����̏ɂ��āx�v�̔��\���e�ɂ��A�����̊C�ݐ��́A�h���ۈ��т�������قǂ��������Ă��炸�A�X���h���{�݂̌������c���Ă��邾���ŁA��n�ƊC���t���b�g��Ԃł��B�Ƃ̂��Ƃł����B
�@���̌�A���ɂ����w�����̌������ɂ��R���ւ̍ĕ҂ŁA������͈ꕔ���������w�������������ɂȂ��āA���Q�O�P�Q�N�S�����{�ɗ������邱�Ƃ͂ł���悤�ɂȂ�܂����B
�@�Q�O�P�Q�N�T���A�u���O�w��Вn�̐_�ЁE���@�֍s�����B�x�ɏ����摺��E�M�z���_�Ёi���̂P�j�i���̂Q�j�̋L���������܂����B
�@�Q�O�P�Q�N�S���P�U���̗[���ɋM�z���_�Ђ�K�˂��ł��B
�@�M�z���_�Ђ͔�Q���Ă��܂�������Ȃ̂ŗ�����Ă͂��Ȃ����A�s�����Ƃ��ł���ƕ�����܂����B
�@�Îl���Ђ͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�G����Ă��܂���ł����B
�@�Îl���_�Ђ�T�K���ׂ������W�ߎn�߂܂����B
�s�T�K�L�^�t
�@�쑊�n�ւ̍s�����E�����摺���Ղւ̌o�H�E�h���{�݁E���̌������K�v�ɂȂ�܂����A���n���E�����M�E���n���̏�̒n�}�m�F�E���A�}���ق̑��������E���A���܂ňȏ�̏����ŗՂ݂܂����B
�@
���Q�O�P�Q�N�P�P���Q�R�`�Q�S���i���Q�S�j�T�K
�@��{��IC���猧���P�Q����ъّ����ʂ��ē쑊�n�ցB
�@������̓쑊�n�s���}���قŁA�w�������j�x�E�w�����u�x��w���͎s�j�E��P�O���x���A����̎������R�s�[�����Ă��������B
�@���w�������������̏����̒��ɓ���Ɣ�Q���ڗ����A���Z�̂ł��Ȃ��X�ɐM�����_�����Ă��܂����B
�@�����U�����ɏo��Ɠ��H�e�ɎԂ�_�@��Ȃǂ��U�����Ă��܂��B�J�����������邱�Ƃ��ł��Ȃ��S��B
�@�ʍs�~�߂̓����I�āA�Ôg�ʼnꂽ�ƕ��݂̓���i�݁A�ʐ^�Ō��Ă����C�ӂ̏������R�̎�O�ŎԂ��~�߂āA�⓹�i�E�Ɍ䓰�E�n���A���ɕ�n�j���̂ڂ�L���쌴��i�݁A���܂����_�Ђɋ߂Â��܂��B
�@���������Ă��|��A�M�z���_�Ђ̔q�a���ׂ�Ă��܂����A�{�a�͂��낤���Ė����̂悤�ł��B
�@�Q���e�̌Îl���_�Ђ̂P�Ԏl���قǂ̎Гa�͖����ł����B
�@�p�ӂ��Ă�����_������܂����B
�@�����Ղ̈ē��̐���������Ɓu�c�����N�i�P�T�X�U�j���n�ˎ��\�Z��`���́v�u�\�܂�z�������߂��炵�܂��ɓa�ɂ����Ă悤�Ƃ����O���A�Ύ����N���ĎR�ς݂����ޖ������܂��D�ɂȂ��Ă��܂����Ɠ`������B�`���͂����s�g�Ƃ��āA���z���ɏ��z���Čc����N�A�����邩��ڂ����B�v�u���{�ېՂɂ͋M�z���_�ЁA�Îl���ЂȂǂ��Ղ��Ă���B�v�Ƃ���܂��B
�@�Îl���_�Ђ̎Гa���ɂ������Ă����R�����J�����Ɏ��߂āA�_�Ђ����Ƃɂ��܂����B
| �@����F �Q�������̒����@�@�E��F ���ɋM�z���_�Ђ̔q�a�A���ɌÎl���ЁA�E�Ɉē��� �@�����F �Îl���_�Ё@�@�E���F �ē��� |
 |
 |
 |
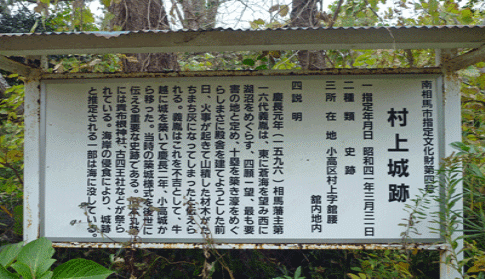 |
�@�y���̑��̎ʐ^�mNEXT�n�{�^�� �z
�@

�@������Ղ��J���鑊�n�����_�Ђ��Q�q���A���n���ċM�D�_�Ђ��Q�q���܂����B
�@������ɖ߂�쑊�n�s�����قɍs���܂����B
�@�������JR���m���w���̃r�W�l�X�z�e���ɏh�����A�w�O�ʂ�ŐH�����Ƃ����̂ł����A���H�X�̊���͓X��߂Ă���X���Ă���X�[�p�[������܂����B
�@�������ɒn�k�B
�@���n�s�̏���Y��K�˂܂����B����Y�勴�߂��̋��`�ɂ͐������̋��D���W������Ă��܂����B���ނ�����Ă���l�B���������܂��B
�@���n�����_�ЂɎQ�q���A���n������Ղ�����Ă��܂����B
�@�A�H�A��{���ɑ�����A��{���隬��K�˂܂����B
�s�T�K�̐����t
�@�Îl���_�Ђ̎Гa�ɂ������Ă����u�Îl���_�Ђ̗R���v�ɂ́A�u�Îl���Ђ��i�q�g�i�r�А\���͐l�c��\�㐒�_�V�c�̒����R���l���ɔh�����č����肵���ւ�͍��j��ł��L���Ȏ����ł���܂��Ă��̎Ђ͎��ɍ��̎l�����R�ɊW������{�ŌÂ̕��k�s�l�̎Ђł���܂��@�����\�ɋ���͂���ꂽ�����͕ʖ��͐l�c�攪��F���V�c�̌䑷�ɍ����ڈΓ������B�[���i�ݓ��点���ɑ���Ɍ�k���l���Ȃ���z���b����ݏ鍟�̎�����ɉ�������̐_�Ƃ��ĎГa��k�ʂ��ĕ��V����ꂽ�镐�_�������̌Îl���Ђł���ƌ×����\���`�ӂ�Ƃ���ł���܂��č������Гa�͑��̂܂ܖk��������Ă���̂ł���܂��@���̎Ђ͌����̏����ɉ��č��ƂƑ厖�ȊW��L�����ӂׂ��Ђł���܂��v
�u�Îl���_�Ђ͖�����N�ȌȂ��q�ρr�N������\�O��������S�\��N�O�ɍČ����ꂽ�_�ЂŌÎl���_�Ђ̓��ɋL������ėL��܂��@�ȑO����ڎR�ɂ������炵���@�@�{��@���n���������k���͉P�Ƃ��������̉��̉��_���M�̕����̂悤�ɒ����L����Ă���l�@��H�����@�k�W�t�S�I�����@���E�q��v�u�Îl���_�АV�z�ψ��@�i�����O�������āj�@���a�Z�\��N�ꌎ��������v�q�k�@�l���͐���ł��r
�@�����摺��̋M�z���_�Ђ̃f�[�^�[�́A
�@�w�����̍Ձx�F�@�M�z���_�Ё@�@�Ր_�@�i��j�����_�i���������݂̂��݁j
�@�\���s���������́A�J�̉��Ɍ����O���ח��������܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����n�@�@�@�@���n�S���������㎚�ړ��P�Q�V
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Z���\���@�@�쑊�n�s�����摺��ړ��P�Q�V
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ЂȂǂ̋L�ڂ͂���܂���
�@�쑊�n�s���}���قŃR�s�[�����Ă�������w�����u�q�����������r�x�ɋA���ɖڂ�ʂ��܂����B
�@�w�����u�x�́A�����́u�����u���v�i���q�v�j�ɂ��u�����u�Ƃ́A���̑��n�Ɋւ���L�^�Ƃ����Ӗ��ł��邪�A���̑��n�Ƃ́A�֓��̑��n�ɑ��Ă̈��ł���B���n���͐�t���̕�����ŁA�Â��͉����ɋ��������A�q���r�����u�̕Ҏ[�́A����̐����I���ɋ߂������l�N�q1858�r����A�˂̎��ƂƂ��Ă͂��߂�ꂽ���̂ł��邪�A�˖��ɂ���Ď�Ƃ��Ă���ɂ�����������͔̂ˎm�֓������i�Ђ낽���j�ł���B�q���r�ꉞ��������܂łɑO��\�ܔN��v���Ă���B�q���r�v�Ƃ���܂��B�l�b�g�Łu�����u�v�ƌ�������ƁA�T�C�g�w���n�f�W�^���~���[�W�A���x�́u�����u�̌��{�v�L�����o�Ă��܂��̂ŁA���Q�Ɖ������B
�@���āA�w�����u�x�������E���㑺�̐_�K�̍��ڂɂ͐悸�u�M�z���_�K�v�̋L�ڂ�����A��������Ɓu�ڃm���ɂ���B���ЁB�K������W���R��y�A�ʓ��C���@�B�v�����N�Ɂu����V�c�掵�c�q�`�ǐe���A�c���i�k�����ƂƋ��ɓ����ɉ������B���Ɨ�R���Ȃċ���ƂȂ��A�e���͊p�����̊ڂɂ���̂�����قƂ��ӁB�c�e���A�����q���������݁r�̐��ՋM�D�̐_���ړ��Ɋ������C��̈��B���F��Ղ鏊�̏����K�Ȃ�B�e�����قɍ݂邱�ƘZ�N�ɂ��ċg�����ɏ㗌�������N��H�݂Č㑺��V�c�ƍ����B�̂ɂ��̒n�𖼂Â��đ���Ƃ����B�v�u�������h�K�N��薈�Ώt�H�̍Փ��ɎДȂɎs�𗧂B�c�c�c���x����Êڂ̓��A�M�D���_�Г������ȗւɉ����āc�V�K�̎s�����Đ\���ׂ��|�A���`�l�v�����Ȃċ��o�����v�����L����Ă��܂��B
�@�㑺��V�c�Ɋ֘A�����n���R���Ɛ_�Бn���R���͒P�Ȃ�`���Ƃ��Ă��A�����ȗւ̑��݂Ǝs�������Ă������Ƃ�������܂��B
�@�����Łu�Îx���_�K�v�̋L�ڂ�����A��������Ɓu�ڃm���ɂ���B�c�ʓ��C���@�B�v�u�Ր_�s�ځB�Îx���̎Ѝ��͐_�Ѝl�y�юЉƂ̓`�L�Ɍ������B�Ðl�H���A�`�ǐe���㑺��V�c���Ղ�A������Ðe���Ə̂��B�㐢�a��ČÎx���ɍ��ƁB���ʓ��@�ɉ����Ă͌ώq���ɍ��B�����������ЂɌÎx�����K����A�������Ր_���ڂȂ�B�v�Ƃ���A��������`�ǐe���ƌ��т��ăR�V�I�E�����l���Ă��܂��B
�@�]�˖����ɂ́A�u�Îx���v�̈�����������Ȃ��Ȃ���I�ȋL�^��������Ԃ�m�邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�Ȃ��A�m�@�̍��ڂɁu����R�C���@�v�̋L�ڂ�����u�O�J�n�ɂ���B���R�J���s�ځB�^���@�v�ێR���{����h�Ȃ�B�{���s�������A�q�B�ʓ��̐_���O�Ɍ���B�v�Ƃ���܂��B
�@�w�����u�x�ł́A�㑺��V�c���u�Ðe���v�Ə̂��J�������̂��u�Îx���v�ɂȂ��āu�ώq���v�Ƃ��\�킳���Ƃ���Ă��܂��B
�@�܂��A�����������ЂɌÎx�����K����̋L�q������܂����A�w�����u�x�̍���̃R�s�[�͈͂Ɂu�F�����E�����v���Ȃ����߁A����ȏ�̂��Ƃ�������܂���B
�@���n�����_�Ђɂ͎Q�q���ۖ��Ђ����Ă��܂������A�Îx�����K�ɂ͋C���t���܂���ł����B
�@�Ċm�F�������Ƃ̎v�������܂��B
�@���݂̎Гa�Ɍf���Ă���u�Îl���_�Ђ̗R���v�����p���ċL���܂������A���̗R�����͂�����Îl���_�ЂƂ����Ђ̒m���������āA�`�ǐe���ɑ���̂Ɠ��l�Ɍ����͕ʖ���̒n�Ɉ����č\������Ă���悤�Ɏv���܂��B
�@�R�`���̌Îl���_�Ђ̗R���̊���ɂ��M�l�q���c�����C�r�̑؍ݓ`��������܂����B
�@
�@����́u�Îl���_�Ёv�́A��Ղ̖����ȗւŎs�����������ƂȂǂŁA���l���_�Ђɐڂ��ė������ƂŁA���Ɏ���܂ňێ�����Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���̍]�ˊ��ɂ��̐_�Ђ�n���̕��́u�Îl���v�ƌ����\���Ă����̂ł��傤���B
�@������N�́i�_�Ёj�Č��̍ۂɂ͉��Ƃ������̐_�Ђ��Č������̂ł��傤�B
�@�_�Ж��ג��ւ̑Ή��͂ǂ̂悤�ɂȂ��ꂽ�̂ł��傤���B���邢�́A���̍ۂɁu�R�V�I�E�v�ɂ��Ă̎w���̂悤�Ȃ��̂��������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��ł��傤���B�����̎����E�L�^�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���B
�@���āA�u�����u�v�ŏ������E�쏬�����́u�ЉƁv�̍��ڂ̍Ō�Ɂu�����F���m���@�����V�ɋ���B�O���l�����N�q�P�W�S�V�r�����\�����A��{�i�c�㎁�������A�Îx���A����ɖk�����������З��Ђ��K������B�Éi�M���N�q�Éi�O�N�E�P�W�T�O�r�܌���\�O���Îx���K�����Փ��㌎��\����B�����l�����N�q�P�W�T�V�r�܌���\�������K�������ߓ��V���Ղ�B�v�ƋL����Ă��܂��B�q����r�͕�L�B
�@�Ȃ��A�������E�������̐_�K�̖����_�K�̍��ڂɌÎx���Ɋւ���L�q�͖����A�쏬�����̐_�K�̍��ڂɂ��Îx���̋L�q�͂���܂���B
�@�����̏o�����ł����A�Îx���͖k�����������Ёq�쏬���ɑ���k�����̖����Ђ��r�Ƃ���܂�����A���������K�̖��Ђŗǂ��ł��傤���A�ǂ��ɂ������̂ł��傤���A���邢�͉Éi�O�N�ɌÎx���K�͂ǂ��Ɍ������ꂽ�̂ł��傤���B
�@�����ɂ����Ђ̌Îx���K���������̂��A���ЂƂ����̂�����̌Îx���K�Ȃ̂��A����Ƃ��������瑺��Ɉڂ����̂��A��ł��B
�@���݂̌Îl���_�ЎГa���V�z���ꂽ���a�U�P�N�q1986�r�̗R�����ɁA��P�P�X�N�O�̖����Q�N�i1869�j�ɍČ����ꂽ�Ƃ̂��Ƃł�����A����ȑO�ɑ��݂��Ă����Гa�͉Éi�R�N�q�P�W�T�O�r�́u�Îx���K�����v�̎Гa�Ƃ������Ƃł��傤���B
�@�Éi�R�N���疾���Q�N�܂ł͂P�X�N�ł�����A�Éi�R�N�����̎Гa�ł���ΘV�����ɂ�錚�ւ��Ƃ͍l���ɂ����̂ŁA�Q�O�N���ƂɌ��ւ���Ƃ��Ď��Ƃ��ʂ̗��R�����������A���邢�͉Éi�R�N�����̎Гa�͕ʂ̏ꏊ�ɍ݂����̂��A�ǂ��Ȃ̂ł��傤���B